長文読解において、「there」と「it」の存在表現は単なる文法知識を超えた重要な意味を持ちます。これらの構文は、学術論文、新聞記事、ビジネス文書、文学作品など、様々なジャンルの長文で頻繁に使用され、情報の提示方法や文章の流れを理解する上で不可欠な要素となっています。
なぜ長文読解で存在表現が重要なのか
長文読解において、存在表現は以下の重要な役割を果たします。第一に、新しい情報の導入と既知の情報への言及を区別する手段として機能し、読者が文章の情報構造を効率的に把握する手がかりとなります。第二に、文章の展開パターンや論理的な流れを示すマーカーとして働き、特に説明文や議論文において重要な役割を果たします。
現代の入試問題やTOEICなどの英語試験では、特に読解セクションでこれらの存在表現を含む文章が頻出し、正確な理解が高得点につながります。また、学術的な文章では、研究結果や問題の存在を客観的に提示するために、これらの構文が効果的に使用されています。
基本構造と長文読解での認識ポイント
存在表現の基本構造には、「there構文」と「it構文」の二つの主要パターンがあり、それぞれ異なる機能と意味を持ちます。長文読解では、これらの構造を瞬時に認識し、文脈に応じた正確な理解を行う能力が求められます。
there構文の機能的特徴
「there構文」は、「何かがある」ことを初めて話題にする際に使用され、冠詞の「a」を使うイメージに近い機能を持ちます。この構文は、新しい情報を文章に導入する際の重要な手段として機能し、読者の注意を新たな要素に向けさせる効果があります。
「there will be」「there must be」「there might be」「there used to be」「there must have been」「there should have been」などの表現は、時制や法助動詞と組み合わせることで、様々な時間的・論理的関係を表現できます。長文読解では、これらの表現を通じて、筆者の推測、期待、過去の状況、理想的な状態などを読み取ることができます。
it構文の機能的特徴
「it構文」は、特定の事柄・場所・事実・状況などを表し、冠詞の「the」を使うイメージに対応します。この構文は、既に言及された内容や文脈で特定可能な事柄に言及する際に使用され、文章の一貫性と結束性を保つ重要な役割を果たします。
「it is + 形容詞 + to + 動詞」の構文では、行動や状況に対する評価や判断を表現し、長文読解において筆者の価値観や立場を理解する手がかりとなります。また、距離・時間・天気を表す際の形式主語としての「it」も、文章の状況設定や背景理解において重要です。
長文での実用的な出現パターン
学術論文での使用
学術論文では、研究上の問題点や課題を提示する際に「there構文」が効果的に使用されます。「There are several limitations in this study」「There remains a need for further research」のような表現は、研究の現状や今後の方向性を示す重要な情報となります。
一方、「it構文」は研究結果の評価や解釈を表現する際に使用されます。「It is important to note that」「It becomes clear that」のような表現は、研究者の判断や結論を明確に示し、読者に対する論理的な説得力を高める効果があります。
新聞記事での使用
新聞記事では、事件や問題の存在を報告する際に「there構文」が多用されます。「There was an accident on the highway」「There will be changes in the policy」のような表現は、読者に新しい情報を効率的に伝える手段として機能します。
記事の分析や評価を行う際には「it構文」が使用されます。「It is difficult to predict」「It seems likely that」のような表現は、記者の分析や専門家の見解を客観的に伝える重要な手段となります。
ビジネス文書での使用
ビジネス文書では、問題や課題の存在を指摘する際に「there構文」が使用されます。「There are concerns about the budget」「There should be improvements in the process」のような表現は、組織の現状分析や改善提案において重要な役割を果たします。
プロジェクトの評価や方針の説明では「it構文」が効果的です。「It is essential to implement the new system」「It would be beneficial to expand the market」のような表現は、ビジネス判断の根拠や推奨事項を明確に示します。
情報の新旧と文章構造の理解
新情報導入のメカニズム
「there構文」による新情報の導入は、長文読解において文章の展開パターンを理解する重要な手がかりとなります。「There is something wrong with the computer」のような表現では、問題の存在が新たに導入され、その後の文章で詳細な説明や解決策が展開されることが予想されます。
長文読解では、「there構文」を見つけた際に、その後に続く文章が新しく導入された要素の詳細説明や発展的議論になることを予測し、読解の効率を向上させることができます。
既知情報への言及パターン
「it構文」による既知情報への言及は、文章の結束性を理解する上で重要です。「There used to be a cinema here, but it closed a few years ago」のような表現では、最初に「there構文」で映画館の存在が導入され、その後「it」でその映画館に言及されています。
このパターンを理解することで、長文読解時に代名詞の指示対象を正確に特定し、文章の論理的な流れを把握することができます。
実践的な読解テクニック
長文読解で存在表現を効果的に理解するためには、段階的なアプローチが重要です。第一段階では、「there」と「it」の即座認識能力を身につけ、それぞれの構文を瞬時に特定します。
第二段階では、情報の新旧判別を行い、新しく導入される情報と既知の情報への言及を区別します。第三段階では、文脈把握として、これらの構文が文章全体の展開や論理構造にどのように貢献しているかを理解します。
設問対策としては、内容理解問題では新情報と既知情報の区別が、推論問題では「there構文」で導入された要素の後続展開の予測が、文構造問題では代名詞の指示対象の特定が特に重要になります。
効果的な学習方法
存在表現を長文読解で活用するための学習方法として、以下のステップが推奨されます。まず、基本的な「there構文」と「it構文」のパターンを完全に理解し、各構文の機能と使用場面を明確にします。
多様なジャンルの文章(学術論文、新聞記事、ビジネス文書、文学作品など)でこれらの構文の使用例に触れることで、実践的な読解力を向上させることができます。また、「there構文」で導入された新情報がその後どのように展開されるかを追跡する練習により、文章の構造的理解を深めることが重要です。
特に重要なのは、これらの構文が示す情報の性質(新情報vs既知情報、具体的事実vs抽象的概念)を正確に判断する能力を身につけることです。この能力により、長文読解時により効率的で正確な理解が可能になります。
まとめ:長文読解力向上への道筋
存在表現「there構文」と「it構文」の理解は、長文読解において情報構造の把握と文章展開の予測を支える重要な文法項目です。単なる構文理解を超えて、新情報の導入、既知情報への言及、文章の論理的流れを読み取るためのツールとして活用することが重要です。
継続的な練習を通じて、これらの構文を「認識する」段階から「理解する」段階、そして「活用する」段階へと発展させることで、長文読解の総合的な能力向上が期待できます。この文法項目をマスターすることは、英語の長文読解において確実なアドバンテージをもたらし、学術的な議論からビジネス文書、ジャーナリスティックな記事まで、幅広い分野での読解能力向上に寄与するでしょう。
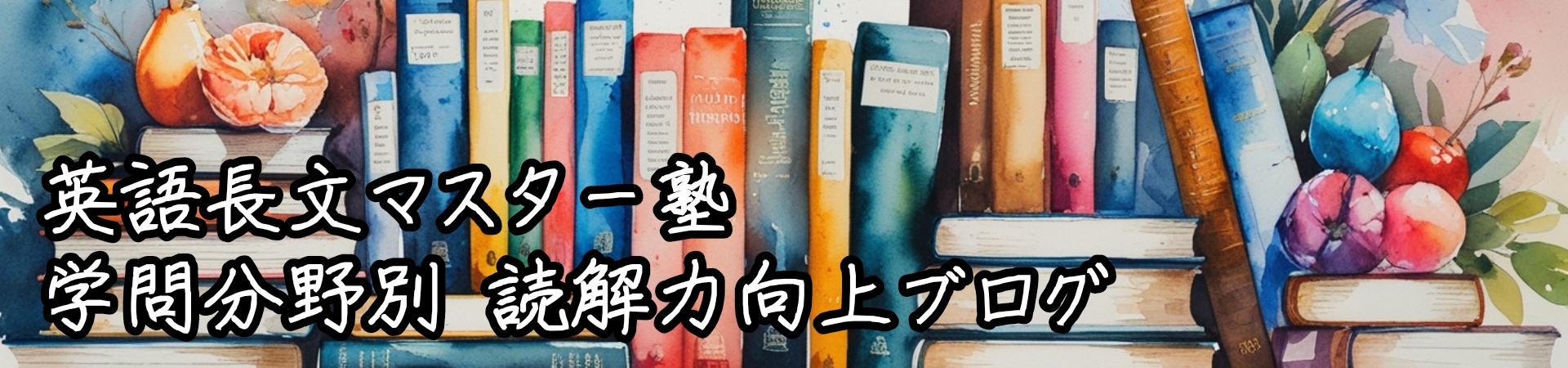
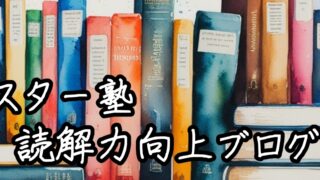
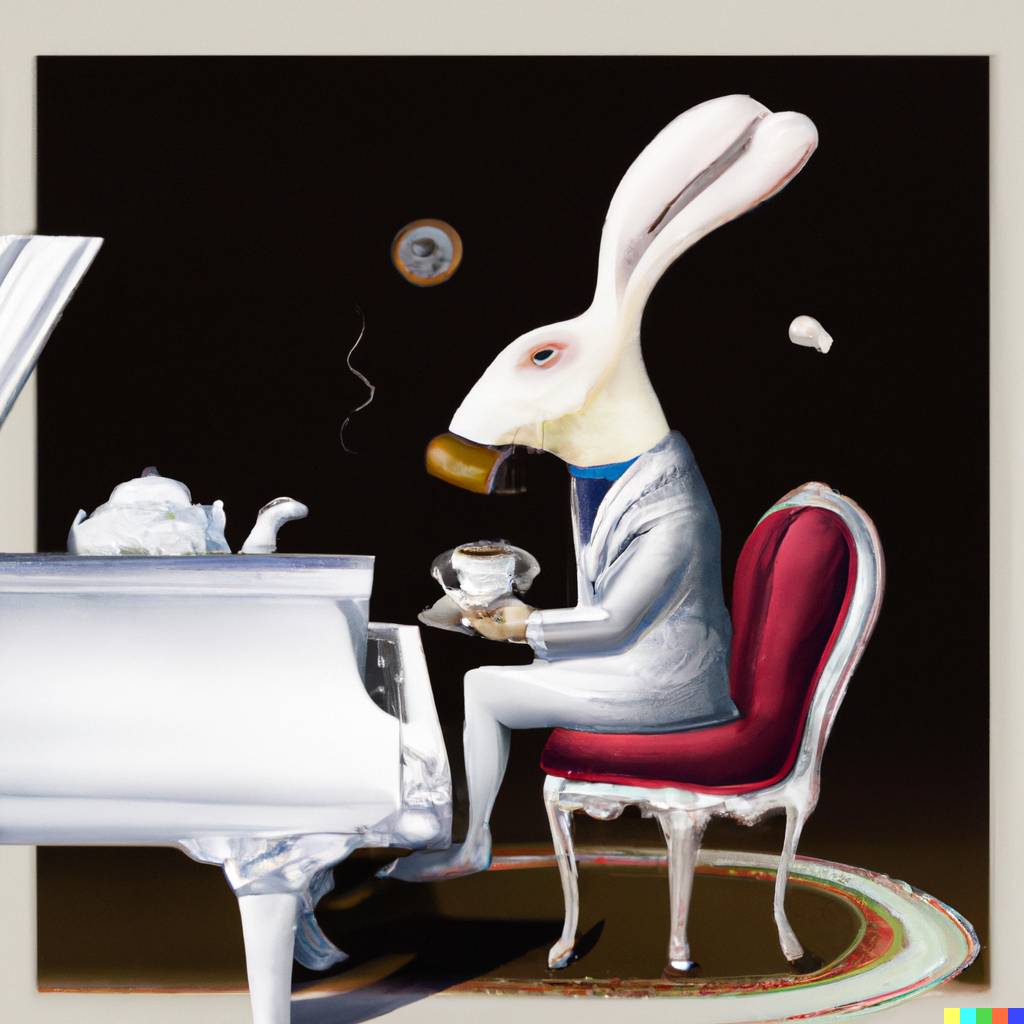
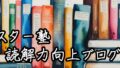
コメント